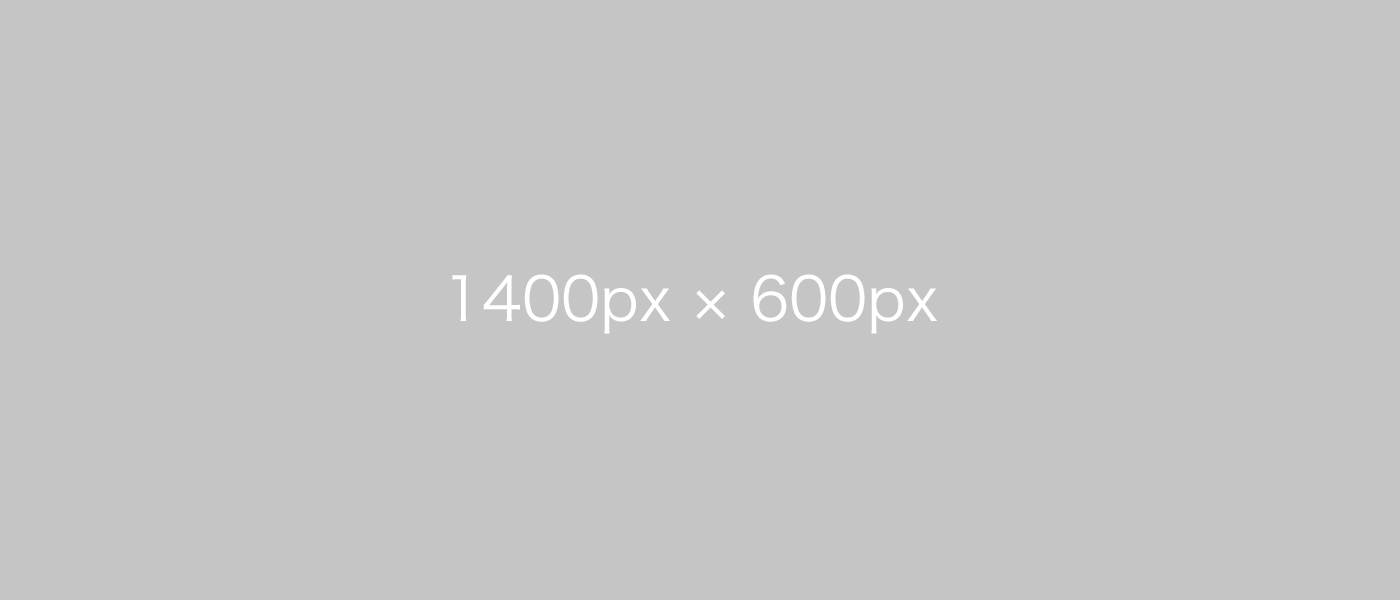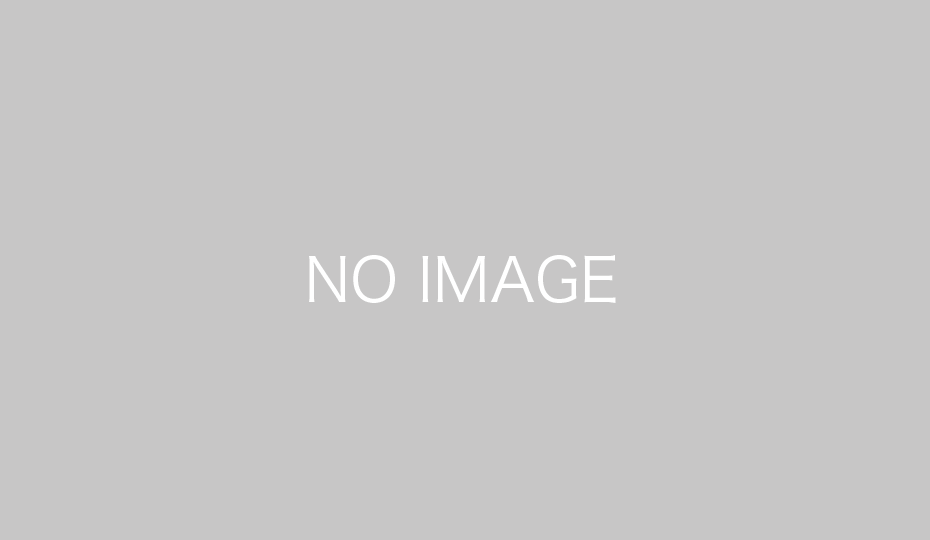大津・晴嵐学区 地域住民が運営
地域住民のボランティアによる大津市北大路の図書室「晴嵐コミュニティ図書」が今年3月、開室50年を迎えた。本の貸し出しや管理、読み聞かせ活動など手づくりの運営を続けており、代表の木下厚子さん(76)は「本に囲まれる環境を子どもたちに、という保護者らの思いがつながってここまでたどり着いた。これからも読書のよさを伝えていきたい」と意気込んでいる。(角川哲朗)
「子どもに本を」思いつながる

同図書室のある晴嵐学区周辺には1970年頃まで図書館や大型の書店がなく、「子どもたちが歩いて行ける範囲に図書館を」と保護者らが中心となって設立に向けて活動を開始。地元自治会などの協力を得て75年3月、市内の公民館から譲り受けた廃棄本約1000冊などを元に晴嵐会館の2階にオープンさせた。本の分類や登録、ラベル貼りなど準備のほとんどを保護者らがボランティアで行うゼロからのスタートだった。
当初は子ども向けの本が中心だったが、幅広い世代に楽しんでもらえるよう年々蔵書を拡充。赤ちゃんの読み聞かせから大人の本まで取りそろえ、現在は晴嵐デイサービスセンターの敷地内に場所を移し、蔵書は約1万2000冊になった。絵本、児童書、大人向けの本がそれぞれ3割ずつを占め、近年では年間約6000冊の貸し出しがあるという。
運営メンバーは現在約30人。地元小学校PTAの力も借り、貸し出しの受け付けや蔵書整理などを分担する。本の購入にはまちづくり協議会の予算などを活用し、毎年約100冊ずつ充実させている。読み聞かせに適した本や個人では買いにくい大型の絵本をはじめ、利用者からのリクエストなどを基に購入図書を決め、メンバーが自ら書店に買いに行く。
開室と同時に子どもたちを対象にしたおはなし会をスタートさせ、メンバーらが定期的に絵本の読み聞かせや人形劇などを開催している。今では同会を年9回、地元の幼稚園の読み聞かせも月1回ほどのペースで行うなど、子どもが本に興味を持てるような取り組みを進めている。
ただ、課題もある。本の管理は50年前から変わらず手書きで、登録や貸し出し管理も紙のカードを使っている。予算や技術的な面からデジタル化を進めるのは難しいといい、メンバーで学校司書の資格を持つ谷かをりさん(63)は「手作りの図書館なので仕方ない部分もあるが、今後も継続して活動していくために対策をみんなで考えていきたい」と話す。
開室から半世紀を超え、「子どもの笑顔がみたいというメンバー共通の思いが原動力」と木下さん。「これからも皆で力を合わせて活動を続け、地域に根ざした図書館として次の世代につないでいくことができれば」と先を見据えている。
開室は水曜(午後2~4時)と土曜(午前10時~正午、午後1~3時)の週2回で、毎月第5週と祝日は休室。市外の人も利用可能で、本は1人5冊まで最大2週間借りることができる。問い合わせは晴嵐コミュニティセンター(077・537・0773)。