プランクトン 写真、動画で解説



琵琶湖のプランクトンを研究する滋賀大名誉教授、石上三雄さん(79)ら3人が共著、出版した「びわ湖のプランクトン フォト&ムービー」(文理閣)を大津市立小中学校全55校に寄贈した。約200種の生態について写真や動画で解説した本で、石上さんは「大人にも子どもにも見てもらい、琵琶湖の生きものに目を向けるきっかけになれば」と話し、ほかの県内の小中学校にも順次寄贈する予定。(角川哲朗)
滋賀大名誉教授ら 大津の小中に寄贈
顕微鏡がなくても気軽にプランクトンを観察できるようにと、石上さんが、県琵琶湖環境科学研究センターの元特命研究員、一瀬諭さん(72)、県立琵琶湖博物館総括学芸員、大塚泰介さん(57)に声をかけ、2021年頃から企画。琵琶湖の位置も深さも様々な場所からプランクトンを採取し撮影を始めた。
本に掲載されているプランクトンは原則、生きた状態を撮影したもの。単にすくった湖水の中から狙ったプランクトンを見つけるのは至難の業で、何度も琵琶湖に足を運び、採取を続けたという。
撮影では様々な種類の顕微鏡を使って、見やすく分かりやすい形になるようにした。動きを止めると死んでしまう種もおり、何度も撮り直したり、同一平面上に複数の個体が並ぶようにしたりと、試行錯誤の上、完成させ、昨年出版した。
本は、原生動物や節足動物、ケイソウなど動植物のプランクトンを分類し、約200種を掲載。形状や生息場所・時期、捕食の方法などを紹介し、写真約500枚を使った。各項にあるQRコードをスマートフォンなどで読み取ると、プランクトンの捕食、排せつ、産卵、
などを捉えた動画約100本が視聴できる。使用されている写真、映像を収めたDVDも付いている。
石上さんは「飛び出す絵本のようなイメージで作った。顕微鏡がなくてもきれいに見られるので、小さな世界をのぞいてほしい」と話し、大塚さんは「琵琶湖のプランクトンに興味を持ち、研究にも関心を持つ人がひとりでも増えてくれれば」と期待している。
A5判並製、214ページ、2750円(税込み)。問い合わせは文理閣(075・351・7553)。

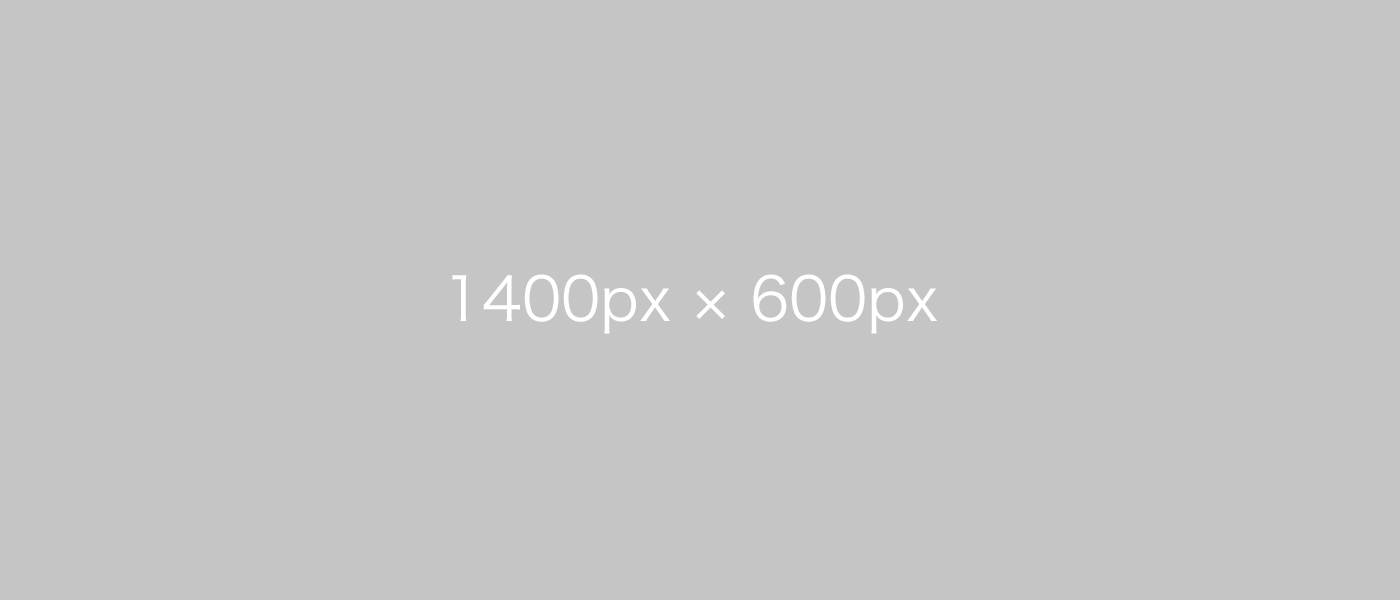
コメント