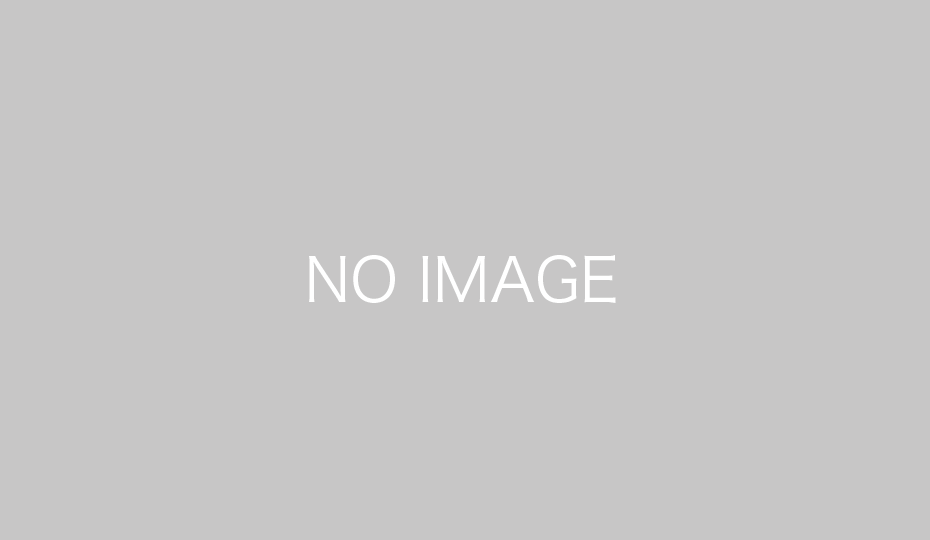流れ速い浅瀬、ヤナギの根に
琵琶湖固有種のコイ科「ホンモロコ」が産卵の際、流れの速い水際に繁茂するヤナギの根を好んで産み付けている実態を、近畿大などの研究グループが調査で確認し、国際誌に発表した。湖岸の開発や外来魚による食害、人為的な水位操作で卵が干上がるなどし、一時は激減したが、近年は産卵環境に配慮した水位の調整などで改善の傾向が表れていた。(名和川徹)
時期配慮した水位調節を



近畿大、滋賀県、京都大の研究者5人のグループで、17日に論文が「フィッシャリーズ サイエンス」(電子版)に掲載された。
ホンモロコは体長10センチ前後に育ち、淡泊な味で素焼きや天ぷら、南蛮漬けなどで食べられる。琵琶湖の特徴的な魚介8種類「琵琶湖八珍」の一つに数えられており、「コイ科の魚では最もおいしい」ともいわれ、料理店などの人気メニューになっている。
漁も盛んで、漁獲量は約30年前までは年間200~400トンで安定していたが、急激に減少。2004年には5トン程度に落ち込んだ。環境省は07年のレッドリストから、絶滅の危険性が極めて高い「絶滅危惧1A」に分類。県なども固有種の重要性や保護を呼びかけている。
産卵にどんな場所を選ぶのかは、生えている植物や流速などの条件が関係している可能性が指摘されていた。しかし、定量的には明らかにされていなかった。
グループは保護する上で産卵環境を詳細に検証することが重要と考え、22年、湖岸域の調査を実施。産卵最盛期の5月に大津市の河口部163か所、守山市の181か所の計344か所に20センチ四方の区画を設定し、区画内で卵の有無や水温、水深、沖から岸に向かう湖水の流速、底質などを測定した。
その結果、卵は水深が浅く流れが速い水際で、繁茂するヤナギの根に多く確認された。一方、根が生えていても流れが遅い区画では卵は見られず、グループの責任者で近畿大農学部の亀甲武志准教授(水産増殖学)は「波が根に打ち寄せ、水中に酸素が行き渡るような所を好むのでは」とみる。
琵琶湖は洪水防止のため、梅雨時期などに水位を下げる操作が行われている。近年は魚の産卵環境の保護を意識し、県や国などが連携。治水、利水に影響しない範囲での水位操作が続けられ、ホンモロコの漁獲量は数年前には三十数トンまで回復している。亀甲准教授は「今後も産卵が多い時期に配慮した水位の調節は重要。卵をしっかり
させることで、回復が進むことが期待される」としている。